「飲食で働いてみよう」と思う人はたくさんいます。 下は16歳の高校生から、上は70代のベテランまで。 ですが──“お店で働く”という言葉のイメージは、人によってまったく違います。
そのイメージが、店長の考える“お店の実態”と一致していないと、店づくりは上手くいきません。 ここに、「お店を回す」ための最初の壁があります。
① イメージのズレが“現場のズレ”を生む
たとえば、ドーナツ屋さんを例にしてみましょう。 多くの人は「ドーナツを作って販売する仕事」だと思って入社します。 しかし店長が今、一番人手を求めているのは── 「朝の納品仕分け」や「店前の清掃」だったりします。 つまり、本人の“想像していた仕事”と“実際に求められる役割”が違うのです。
これはどんな業態でも起こります。 たとえばイタリアンレストラン。 大学生のスタッフは「パスタを作れるかな」「ピザのトッピングしてみたいな」と思って入ってきます。 でも店長は、今求めているのは「ランチタイムのサラダ補充」「皿洗いのスピードアップ」だったりする。
このズレを放置したままでは、どれだけ教育しても噛み合いません。 店長が描く“お店のシステム”を、どうやってスタッフと共有するか。 そこが「お店を回す」ための出発点です。
② 「全体像」を見せるのが店長の仕事
店長の頭の中には、理想の流れがあります。 開店準備 → 接客 → 仕込み → 片付け → 翌日の段取り。 しかし多くのスタッフは、その全体像を見ていません。
だからこそ、店長は“自分の描くお店のシステム”を、言葉と行動で見せる必要があります。
- なぜその作業が必要なのかを説明する
- 順序・目的・意味を、できるだけ可視化する
- 「お客様に届くまでの流れ」を一緒に確認する
スタッフは“点”で働き、店長は“線”で考えます。 この線を、誰もが共有できるように整えること── それがシステムづくりであり、「お店を回す」第一歩です。
リーダーの言葉が“軸”になる
料理学校では、昔はこのように教えたそうです。
「店長・料理長は神さまである」と。
今ではコンプライアンスの観点から、このような表現は使いません。 けれども、その言葉の裏には、ある大切な意味が込められていました。
それは──「責任者の言うことを聞く、それが任務である」という考え方です。
もちろん、そこにはセクハラやパワハラといった理不尽な上下関係は一切存在してはいけません。
しかし、チームで動く現場では、最終的な判断を担う“軸”が必要です。
店長や料理長の指示とは、「支配」ではなく「責任を背負った決断」です。 その決断に従うということは、現場の流れを止めずに前へ進めるための「プロとしての約束」でもあるのです。
つまり、「指示に従う」=「信頼して任務を遂行する」という姿勢。 これを全員が理解したとき、初めてお店は“同じリズムで回る”ようになります。
④ 「躾」と「業務」は別もの
責任者が「朝、元気よく笑顔で『おはようございます』と挨拶してください」と伝えたとします。 これを“躾(しつけ)”と捉えて、やらない人がいます。
しかしそれは、「職場を動かすための業務」です。 挨拶は「人間教育」ではなく、「チームを円滑に動かすための連絡行為」です。 職場の空気を整え、情報を交わすための最低限の“仕事の始まり”なのです。
同じように、「ユニフォームはこのように着用してください」という指示も、感情ではなく業務上のルールです。
清潔さ・統一感・安心感──これらはすべて「お客様に見せるお店の品質」を守るための要素。 つまり、店長が求めているのは礼儀ではなく、機能なのです。
「お店を回す」ということは、この“当たり前の行動”を共通言語に変えることでもあります。 それを理解して動けるスタッフが増えるほど、現場は静かに、そして確実に整っていきます。
③ 伝える力が、システムを動かす
どんなに優れた仕組みを作っても、伝わらなければ動きません。
店長が持つ「理想のお店の絵」を、どうスタッフに“体感”させるか。 その方法を考えるのが、リーダーの仕事です。
- 見本を見せる(Show)
- 一緒にやる(Do)
- 任せて確認する(Check)
システムとは、指示書ではなく“共通理解の地図”です。
その地図をどれだけ共有できるかが、「お店を回す」力の差になります。
💡まとめ:
「お店を回す」とは、“全員が同じ絵を見て動く”ということ。
そのために、店長は理想のシステムを「見せて・伝えて・理解させる」。
お店は人で動きますが、人を動かすのは“共通の理解”です。

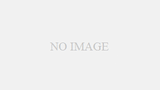

コメント